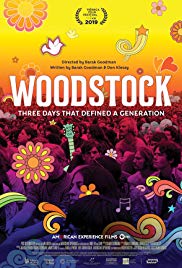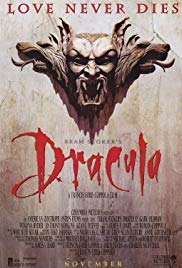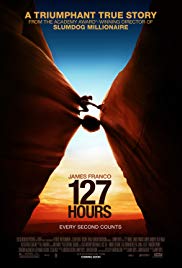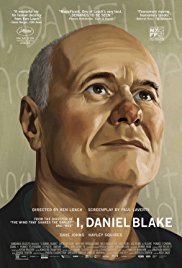暴君の命を奪う命令を受けた男と、暴君の命を何としても守る男。侍同士の面目をかけた戦いは頭脳戦から始まり最後には激しい戦いへと変わっていきました。侍の一分をかけた戦いは激戦のラスト30分で全て描かれていました。
『十三人の刺客』作品情報

| タイトル | 十三人の刺客 |
| 監督 | 工藤栄一 |
| 公開 | 1963年12月7日 |
| 製作国 | 日本 |
| 時間 | 2時間05分 |
『十三人の刺客』あらすじ
[aside type=”normal”]
将軍の弟で明石藩主である暴君を抹殺するべく、刺客が送られた。
13人の暗殺隊は、宿場を出口のない迷路に作りかえ、数に勝る明石藩の武士たちを迎え撃つ。
やがて宿場に到着した獲物と刺客たちの壮絶な死闘が始まった…。
(出典:https://movie-tsutaya.tsite.jp/netdvd/dvd/goodsDetail.do?titleID=0080248712&pT=null)
[/aside]
暴君 松平 斉韶

出典:IMDb
『十三人の刺客』の中で暴君として描かれている明石藩の藩主松平斉韶。
参勤交代中に立ち寄った尾張で尾張藩の牧野妥女の妻を自分のものにし、さらには牧野妥女を刀で斬ってしまいます。
また容赦なく子供までも斬ってしまうとんでもない暴君である松平斉韶に嫌気がさした部下の間宮図書が切腹したことから事件は始まります。
間宮図書の残した遺書であり訴状には、松平斉韶の暴君ぶりが記されていました。
実際に明石藩の7代目藩主であった松平斉韶ですが、彼は暴君ではなかったようです。
あくまで『十三人の刺客』の中に描かれる松平斉韶は、フィクションです。
映画の中では松平斉韶は徳川家慶の弟ではありませんでした。
徳川家慶の弟にあたり暴君ぎみだったのは明石藩の8代目藩主の松平 斉宣の方でした。
松平 斉宣が残した逸話の中に参勤交代中の尾張で3歳の子供が行列の前を横切り、その子供を処刑したという話があります。
これが『十三人の刺客』の元にもなっています。
さらにお金の使い方も荒かったようで、明石藩の財政は厳しかったようです。
そんな松平 斉宣の話をもとにして暴君ぶりを描いののが、『十三人の刺客』です。
侍の頭脳戦

出典:IMDb
剣豪とされ上司からも部下からも慕われている侍は、頭脳明晰と言えます。
この作品の中の島田新左衛門と鬼頭半兵衛も頭脳明晰な侍でした。
松平斉韶の命を狙う島田新左衛門。
島田新左衛門から殿である松平斉韶の命を守る鬼頭半兵衛。
どちらも用意周到に準備をし、作戦を練ります。
参勤交代中に松平斉韶を狙うことにした島田新左衛門は、川を渡る時をチャンスとし仲間とともにその時を待ちます。
しかしその場が危険であると察知していた鬼頭半兵衛は、殿の乗るカゴを2つ用意し影武者作戦に出ます。
しかも警備も厳重にした川を渡った鬼頭半兵衛に対して、島田新左衛門は手を出すことができませんでした。
島田新左衛門も鬼頭半兵衛の作戦を「さすが半兵衛」と評価していました。
一回しかないチャンスを物にすべく島田新左衛門を新たな作戦を立て、松平斉韶一行を待ちます。
松平斉韶の性格をわかっている島田新左衛門は巧みに彼を誘導し自分たちがいる宿場へ誘いこんだのでした。
この宿場には島田新左衛門達が準備した罠が仕掛けられていました。
五十三人に対して十三人で挑む戦い。
失敗するわけにはいかない戦いのために島田新左衛門は周到な準備をしていたのでした。
鬼頭半兵衛も「しまった」と思い引き返そうとしますが、すでに罠にハマった後だったのです。
そしてここから十三人vs五十三人の壮絶なった戦いが始まるのでした。
侍の一分
自分の命にかけて松平斉韶の暗殺の命を受けた島田新左衛門。
彼は松平斉韶を待ち伏せ、彼を刀で斬りました。
これで彼の仕事は終わったのですが、目の前には刀を自分に向けている鬼頭半兵衛がいます。
鬼頭半兵衛に「一対一」でと戦いを申し出た島田新左衛門ですが、刀で斬ってくる鬼頭半兵衛に刀を出さず、半兵衛の刀を受けます。
「なぜだ」と驚く半兵衛に「松平斉韶をうたなければ私の侍の一分が立たない。お前は私をうた負ければ侍の一分が立たない」と言います。
島田新左衛門は自分の侍の一分がたった後、半兵衛の侍の一分を立てるために自ら彼に斬られたのでした。
半兵衛は結局刺客の一人に槍で刺されてしまいますが、島田新左衛門も鬼頭半兵衛の侍の一分の玉目に命をかけて戦ったのでした。
まとめ
侍同士の面目をかけた戦いを描いた『十三人の刺客』。
ラスト30分の戦いは時代劇映画の中でも歴史の残る場面となっています。
激しい戦いの中で揉みくちゃになりながら必死で戦う男達。
彼らの覚悟と勢いが感じられる場面となっていました。
当時の侍は侍の一分のためだけに生きそして散っていったのかもしれません。
壮絶な戦いの後に残ったのは切なく悲しい心情でした。
そしてそれは生き残った侍みんな同じ気持ちだったのかもしれません。